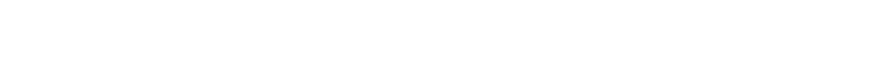DMCシンポジウム2022

お申込はこちらをクリック
「デジタルの本質とはなにか――メタバースに向かう中で考える」

主 催:慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ(DMC)統合研究センター
開催日時:2022年11月22日(火)14:00-16:30(デモは13:00-14:00/16:30-17:00)
開催場所:慶應義塾大学日吉キャンパス 来往舎 シンポジウムスペース(アクセス ※日吉キャンパスマップ⑨番が来往舎です)
オンラインのハイブリッド形式で開催
デジタル技術は、われわれの暮らしに年々さまざまな新しい可能性をもたらしてきました。
これまでのDMCの主たる活動だけを取り上げても、デジタルシネマやCineGridを通した高精細映像表現、キャンパスミュージアムや慶應義塾ミュージアム・コモンズ(Keio Museum Commons)を通した分野横断的ミュージアム、FutureLearn(慶應義塾大学がオンラインコースを公開しているグローバルソーシャルラーニングプラットフォーム)を通した教室に限定されない学びの場の構築の実践が挙げられます。
昨今、社会で喧伝されているメタバースは、デジタル技術の活用の場の広がりへの期待を背景としたものと考えられます。
本シンポジウムでは、多様なバックグラウンドを持ちつつ10年以上にわたり実践的にデジタルと向き合ってきたDMCの研究者たちが、それぞれの経験からデジタルの可能性や限界を語り合います。
―― 当日の様子はこちらからご覧ください ――
プログラム
| 14:00-14:15 | ||
| ご挨拶 | ||
| 岡田 英史(慶應義塾 常任理事) 大川 恵子(慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科 教授(Ph.D.)/DMC研究センター 所長) |
||
| 14:15- 14:30 | ||
| はじめに | ||
 |
金子 晋丈 DMC研究センター 副所長 慶應義塾大学 理工学部 准教授(Ph.D.) 専門:データネットワーキング、アプリケーション指向ネットワーキング。 |
|
| メタバースに至るまでのデジタル技術の発展の経緯や、情報工学からみたメタバースの捉え方を紹介します。 |
||
| 14:30- 14:45 | ||
| キーノート | ||
 |
松田 隆美 慶應義塾大学 文学部 教授(Ph.D.) 慶應義塾 ミュージアム・コモンズ(KeMCo) 機構長 専門:中世英文学、表象文化史、書物史。 |
|
| デジタルというメディアテクノロジーと書物というメディアテクノロジーの違いや共通点から、デジタルの本質に書物誌の研究者が迫ります。
|
||
| 14:45- 16:30 | ||
| パネルディスカッション | ||
 |
金子 晋丈(コーディネーター) DMC研究センター 副所長 慶應義塾大学 理工学部 准教授(Ph.D.) 専門:アプリケーション指向ネットワーキング、分散型ネットワークシステム。 |
|
 |
松田 隆美 慶應義塾大学 文学部 教授(Ph.D.) 慶應義塾 ミュージアム・コモンズ(KeMCo)機構長 専門:中世英文学、表象文化史、書物史。 |
|
 |
大川 恵子 DMC研究センター 所長 慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科 教授(Ph.D.) 専門:デジタルコミュニケーションと教育環境。 |
|
| 学びの場においてデジタルコミュニケーションが担う役割や可能性について考えていきます。 |
||
 |
安藤 広道 慶應義塾大学 文学部 教授 専門:先史考古学、近現代考古学、博物館学。 |
|
| ものや場所というアナログを対象とした学問におけるデジタル技術の適用の可能性を模索してきた経験をもとに、デジタルが届かない点や見逃してきた点はないのかを考えます。
|
||
 |
杉浦 裕太 慶應義塾大学 理工学部 准教授(Ph.D.) 専門:バーチャルリアリティ、実世界インタフェース、ライフスタイルコンピューティング。 |
|
| メタバース空間において、(1)運動リハビリテーションプログラム生成に向けた人間のモーション生成、(2)複数人でできる空間設計、(3)インタラクティブシステムのためのプロトタイピング支援の研究事例の紹介を通して、アナログにないデジタル技術の優位性、可能性は何かを議論します。
|
||
| 16:25- 16:30 | ||
| 終わりに | ||
| 徳永 聡子(慶應義塾大学 文学部 教授(Ph.D.)/DMC研究センター 副所長) | ||
| 13:00- 14:00/16:30- 17:00 | ||
| 研究デモ | ||
| 杉浦 裕太(慶應義塾大学 理工学部 准教授(Ph.D.))研究発表ブース(出展予定) | ||
| ・・・その他のデモが増える可能性がございます。 | ||